📌 記事構成(目次)
- ⭐はじめに
2度目の優勝に込めた想いと、この記事の目的 - 🏆 アマテラス杯とは?
大会の概要・出場条件・スケジュールの基礎情報 - 🔎 優勝から遠ざかっていた理由と向き合い方
構成に対する迷いや環境とのズレ、自分なりの修正と再起 - 🛠 使用した構成と構築のこだわり
スタメン・フォーメーション・連携の選定理由 - 📊 環境上位カードの傾向と考察
2025夏大会で特に多く見かけた強カードや構成、その対応策 - ⚔️ トーナメントで意識した立ち回り
各ラウンドごとの戦い方、勝ち切るために意識したこと - 🧩 構成を再現するうえでのポイント
手持ちやクラブリンクの有無に左右されない再現の工夫、代替選手や連携の作り方 - 🎮 アマテラス杯に向けた普段のプレイと準備
普段からの準備できること、今後のチーム育成へのアドバイス - 💬 これから挑戦するプレイヤーへ
自分の経験から伝えたいアドバイスと応援のメッセージ
⭐はじめに
こんにちは、Jリーグクラブチャンピオンシップをこよなく愛するプレイヤー、ルーカスあきです。
2025年夏、6大会ぶりにアマテラス杯で再び優勝することができました。 画面を見つめながら、静かにガッツポーズしていた自分がいました。
初めての優勝から何度も挑んで、あと一歩?届かない悔しさを味わい続けてきたこの1年半。構成を変え、プレイを見直し、何より自分と向き合ってきた時間が、ついに結果として返ってきた。その感動と手応えを、この記事で伝えたいと思います。
ここでは、自分のチーム構成や戦い方の工夫はもちろん、環境分析や反省から学んだことまで、ありのままを書きました。
これからアマテラス杯に挑戦する方にとって、少しでもヒントや勇気につながれば嬉しいです。
🏆 アマテラス杯とは?
🏆 アマテラス杯の概要
毎月開催されるJリーグとは違い、
全プレイヤーの勝者を決めるJリーグクラブチャンピオンシップ内で真の王者を決める公式大会。
予選リーグを勝ち抜いたプレイヤーがトーナメント形式で競い合い、最終的な優勝者を決定。
アマテラス杯 参加方法とスケジュール
「アマテラス杯」に参加するには…
- リーグ戦で上位に入って「グランドマスター」に昇格!
- 「グランドマスター」のリーグ戦(アマテラス杯予選)で出場権を持っていないチームの中で最も高い順位でアマテラス杯出場決定!
- 出場決定で100バモ獲得!
📅 スケジュール(2025年夏大会)
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 4月14日(月) | アマテラス杯 予選① 開始 |
| 4月21日(月) | アマテラス杯 予選② 開始 |
| 4月28日(月) | アマテラス杯 予選③ 開始 |
| 5月12日(月) | アマテラス杯 予選④ 開始 |
| 5月19日(月) | アマテラス杯 予選⑤ 開始 |
| 5月26日(月) | アマテラス杯 予選⑥ 開始 |
| 6月9日(月) | アマテラス杯 予選⑦ 開始 |
| 6月16日(月) | アマテラス杯 本選 開始🌟 |
📢 本戦について
▼ 「ファイナル」に出場するには…
🔹 1〜3日目:プレミアムステージ
- 試合で勝って勝ち点を獲得!
- 勝利で3点、引き分けで1点をゲット!
- 勝ち点上位1024位以内でトーナメント進出!
🔹 4〜6日目:勝ち抜きトーナメント
- 2試合の合計点勝負!
- 負けたら即敗退の真剣勝負!
▼ 最後まで勝ち残ればファイナルに出場!
勝負は1試合のみで決着!!!
🎯 大会豪華賞品(2025夏)
🟨 天照・攻(センスアイテム)
- 天照・攻(センスアイテム)は、フュージョン用アイテムです。
- フュージョンで使用するとWセンス「天照・攻」を獲得できます。
🔹 天照・攻 の効果
- EP獲得量が50%アップ
- 選手のオフェンス値が20%アップ
🏅 アマテラス杯 報酬一覧(2025夏)
🔹 優勝
- アマテラス杯勲章(優勝:2025夏) ×1
- バモ(VM) ×1000
- 天照・攻(センスアイテム) ×2
- グローリースパイク(金) ×1
🔹 準優勝
- アマテラス杯勲章(準優勝:2025夏) ×1
- バモ(VM) ×500
- 天照・攻(センスアイテム) ×2
- グローリースパイク(金) ×1
🔹 ベスト16
- アマテラス杯勲章(ベスト16:2025夏) ×1
- バモ(VM) ×150
- 天照・攻(センスアイテム) ×1
- グローリースパイク(金) ×1
🔹 ベスト128
- アマテラス杯勲章(ベスト128:2025夏) ×1
- バモ(VM) ×100
- 天照・攻(センスアイテム) ×1
- グローリースパイク(金) ×1
🔹 ベスト1024
- アマテラス杯勲章(ベスト1024:2025夏) ×1
- バモ(VM) ×50
- グローリースパイク(金) ×1
🔹 プレミアム
- アマテラス杯勲章(プレミアム:2025夏) ×1
- バモ(VM) ×30
- グローリースパイク(銀) ×1
🔎 優勝から遠ざかっていた理由と向き合い方
アマテラス杯で初めて優勝したときの瞬間は今でも忘れませんが、それから優勝が遠のいていました。
初回優勝の後の大会ではなかなか結果が出ず、第2回から第6回まではトーナメントの序盤で敗退することもありました。 「初回の優勝はマグレだったのかもしれない」――そう思うこともありました。
環境がTSSのCF中心にシフトしていくなかで、自分のやり方にこだわり続けたことも、勝ちきれなかった一因だったと思います。 流れに乗った方が楽だとわかっていても、簡単には自分のこだわりを変えずに固執しました。 こだわりを捨ててそのまま環境に合わせることもしたくなかったので厳しい期間が続きました。
とはいえ、時間とともに新カードの登場によってこだわりを継続しながら勝つ方法を模索することができました。 また試合の振り返りを重ねて、自分の組み方にどんなズレがあるのかを冷静に見るようにしました。
それに加えてこのルーカスの瓦版の攻略法を掲載することで、自分の考えや勝ち筋も整理されました。 その積み重ねが、今回の優勝につながったのだと思います。
🛠 使用した構成と構築のこだわり
今回の構成は、基本に立ち返って「4-3-3B」を採用しました。フォーメーション選びについては色々試してきましたが、アマテラス杯は2試合の合計結果というルール上、攻守のバランスと安定感とを考えました。
クラブはヴィッセル神戸を軸に構成。理由は単純で、手持ちのカードとクラブリンクの相性が良く、連携やスキル発動の安定感が高かったからです。
構築の中で特に意識したのは、「城塞構築」+「ファイター」「フィニッシャー」の組み合わせ。これは自分が以前からブログでも紹介している「虎の巻」の考え方をベースにしています。
これは迷走していたときに守備陣の後半のスタミナ切れからの守備崩壊の経験から導いた戦略です。
特にGKには前川黛也を採用。ステータス面では他にも選択肢はありましたが、「クラブリンク」「城塞構築」「タイプスターズ(テクニック)」との連携を優先し、構成全体のバランスを重視しました。
後半にスタミナを維持できる「ファイター」や「フィニッシャー」持ちの選手を軸に据えることで、交代枠を無理に使わずに連携を維持しやすい狙いです。守備の起点としてのGKと、テクニック中心の連携軸が今回の構築テーマです。
▼使用スタメンまとめ(11名)
| ポジション | 選手名 | クラブリンク | 連携 |
|---|---|---|---|
| GK | 前川黛也 | ◎ | 城塞構築 / タイプスターズ(TEC) |
| CB | マテウス トゥーレル | ◎ | 城塞構築 |
| CB | 犬飼智也 | タイプスターズ(TEC) | |
| SB(左) | 佐々木翔 | タイプスターズ(TEC) | |
| SB(右) | 酒井高徳 | ◎ | 城塞構築 |
| DMF | 大崎玲央 | 〇 | タイプスターズ(TEC) |
| DMF | 阿部勇樹 | ||
| OMF | 小林祐希 | ◎ | タイプスターズ(TEC) |
| WG(左) | アンドレス イニエスタ | ◎ | タイプスターズ(TEC) |
| WG(右) | 武藤嘉紀 | ◎ | |
| CF | ダビド ビジャ | ◎ | タイプスターズ(TEC) |
本来、小林祐希とダビド ビジャでは「イリュージョン」というオフェンス連携が発動可能でしたが、より強力な「城塞構築」と「タイプスターズ」の発動の妨げになるため、あえて設定しませんでした。
表を見ての通り、連携は11名中8名が発動、クラブリンクも8名が一致。どちらの要素も入っていないのはDMFの阿部のみという構成になっています。
個人的にはベストゴール犬飼を獲得できたのがターニングポイントだと思っています。テクニックタイプかつファイターを持っていたベストゴール犬飼は現状を打開してくれるカードだと当時すぐ取り、気合でチャレンジマッチでキラにしました。そこから守備が安定して実際25年の1月のJ1も制覇できました。
活躍が目立った選手は3トップのほか、「大崎玲央」と「佐々木翔」です。
大崎に関しては、隣に配置したTSS阿部勇樹と同じか、それ以上の活躍を見せました。
スキル構成は以下の3つで、特段目立った能力構成というわけではありません:
- スカイエンペラー
- ピンポイントタックル
- パーフェクトスティール
DEF値も約1600と、現環境においてはむしろ低めの部類に入ります。
それでもTSS選手に対してピンポイントタックルを的確に決め、スカイエンペラーでカウンターの起点にもなっていました。 おそらくクラブリンクには数値化されない裏パラメータが存在しており、それがパフォーマンスに大きく影響しているのではと感じています。
実は直前までつけていたセンスが微妙で、ほとんど使っていなかったのですが、先月のJリーグで試しに採用したところ、 ソックスレベルも低い状態で無双していたため再評価。今回のアマテラス杯ではソックスMAX&スパイク投入で仕上げたことで、さらに能力が引き出されました。
佐々木翔については、あえて多く語る必要もないかもしれません。テクニックタイプでタイプスターズが発動するため、後半でも安定したパフォーマンスを発揮。 今回も期待を裏切らないどころか、“最強”と表現して差し支えない働きをしてくれました。
※佐々木翔の詳細については、次の章で個別に掘り下げて解説します。
✅ 筆者の構成まとめ
この構成では、特別な選手に依存せずとも、全体のリンクと連携を意識することで、バランスの取れた戦い方ができることを再確認できました。 安定した連携・スキル発動・スタミナ管理が、2戦合計制というルール下でも安定感につながり、構築テーマに合致した形で優勝を狙えたと思います。
あくまで私の例ですが、構築考え方の参考になったのではないでしょうか。意外な選手がチームにフィットするかもしれません。上位プレイヤーのカードで使用率が低いカードが逆に注目すると面白いかもしれません。自分なりの戦略を考えてチーム構成するのが醍醐味かと思います。
📊 環境上位カードの傾向と考察
今回の大会では、TSS大黒将志が得点ランキング上位に何度も登場しており、CFによる中央からの決定力が依然として環境を支配していることがわかります。
また以前も考察しましたが、各ユーザーも何かしらのTSSのCFを利用しているので、以前よりCFでの差というものは縮まったということです。
| 種別 | 得点ランキング(選手名) | 種別 | アシストランキング(選手名) |
|---|---|---|---|
| TSS | ダビド ビジャ | TSS | イニエスタ |
| TSS | 大黒将志(G大阪) | TSS | 久保建英 |
| TSS | ストイチコフ | AWS | 武藤嘉紀 |
| TSS | 大黒将志(代表) | REG | マルシーニョ |
| TSS | 大黒将志(G大阪) | TSS | 朴智星 |
| TSS | 大黒将志(G大阪) | SFP | 毎熊晟矢 |
| TSS | 大黒将志(G大阪) | TSS | 久保建英 |
| TSS | 大黒将志(G大阪) | TSS | イニエスタ |
| TSS | 大黒将志(代表) | JP | 三笘薫 |
| TSS | ダビド ビジャ | TSS | 相馬勇紀 |
一方、アシストランキングを見てみると、イニエスタや久保建英、武藤嘉紀、相馬勇紀、三笘薫など、すべてWG(ウイング)選手たちが上位を占めていました。
この傾向からわかるのは、「得点の主役は中央でも、アシストの起点はサイドにある」というこのゲームならではの構造です。
つまり、サイドを支配することが試合の流れを左右する最大のポイントであり、逆に言えば守備も含め「サイドを制する者が試合を制す」と言っても過言ではありません。
筆者の構成は前回大会も両WGがアシストランキング1位と3位を獲得しており、このゲームの構造を抑えているともいえます。
ただこれはイニエスタと武藤の力だけでなく、サイドを制するためにはSBの力のおかげでアシストランキングを上位獲得しています。
この環境に対して、筆者の構成では左SBの佐々木翔を起用。
テクニックタイプかつ「タイプスターズ(TEC)」が発動可能で、スタミナも安定しており、後半でもパフォーマンスが落ちにくい点が決め手でした。
特に、TSS大黒などへのクロスを供給してくるWGを確実に止める場面が多く、 「攻撃の芽をサイドで潰すことで中央を機能不全にする」という守備プランが何度もハマりました。
クロス供給を潰すということでカスタムセンスは「積極プレス」でセレクトスキルは「空中戦の競り合い」を採用しました。
逆サイドの酒井高徳も、城塞構築とクラブリンクの強さでサイドの守備を制して、武藤に繋げました。
今大会のデータは「サイドを制するものが強い」ということを強く物語っており、 それに対してしっかり守備対策を講じたことが、構築全体の安定と勝因につながったと感じています。
⚔️ トーナメントで意識した立ち回り
このゲームの特性として、調子のようなものが存在すると筆者は考察しています。これは毎月のJリーグでも発生するのですが、チーム構成はまったく変えていないのにも関わらず1日目と2日目の成績が大きく変わることがあります。
▼過去の筆者のJリーグの例
- 1日目:8勝2分7敗(勝ち点26/得失点差−2)
- 2日目:12勝3分2敗(勝ち点39/得失点差+27)
上記のような経験が何度もあり、おそらく調子のような裏パラメータやジャイキリがあると思っています。(ジャイアントキリングというセンスがあることも踏まえるとおそらくある)
何が言いたいかというと、予選で一喜一憂しないということ。調子やジャイキリで本来の力が出せないことがあるので、1試合負けただけでコロコロとフォーメーションや構成を大きくいじらない方が良いと考えます。
実際に今回の決勝も、予選33位と34位の対決という展開でした。過去の大会でも予選全勝したプレイヤーが必ずしも決勝に進出しているわけではありません。
むしろ、予選で調子が悪いぐらいの方が、トーナメント本戦で調子が上がって勝ち進む可能性すらあると思っています。予選で多少の負けがあっても、1026位や126位といったボーダーを超える計算だけを意識しておけば十分です。1026位突破の目安は9勝前後。
ここからは、トーナメントでの戦い方の話になります。
アマテラス杯のトーナメントでは、2試合合計スコア制(同点の場合はPK)というルールの特性を踏まえ、1戦目と2戦目の交代カードの使い方が非常に重要になります。
たとえば、1試合目で大きく勝った場合は2試合目ではあえて構成を変えず、守備を意識した慎重な運びにシフト。 一方で1試合目が僅差だった場合やビハインドの場合は、2試合目では後半からより攻撃的なWGを投入し、流れを一気に引き寄せるテンポアップを仕掛けました。
交代カードについては、スタミナではなく連携を守るための交代を基本方針としつつ、試合によって柔軟に対応。2試合通しての戦い方を重視しました。
僅差の場合はPK戦のことも考慮しなければいけません。PK戦では総合力――特に攻撃メンバーの能力が勝敗に大きく関係していると感じています。
相手の攻撃陣との総合力に乖離がある場合、PKにもつれ込んでしまうと勝ち目は限りなく薄くなります。ジャイアントキリングが発生する一方で、やはり総合力が高いチームにはそれだけのアドバンテージがあるということです。
交代や構成で“悪あがき”はできますが、最終的には運に任せるしかないです。
総じて言えるのは、トーナメントでは交代枠をうまく活用すること、そして「プランAで勝つ」だけでなく、「プランBやCへいつ切り替えるか」が鍵になるということです。
🧩 構成を再現するうえでのポイント
今回紹介した構成は、「強カードがなければ真似できない」と思われがちかもしれませんが、実は連携の選定とセンスの割り切り次第でかなりの部分が再現可能です。
✅ 再現性が高い要素
- タイプスターズやクラブスターズなどの“汎用チーム連携”
発動条件がわかりやすく、各タイプの選手は手持ちに6選手以上いる確率も高いため、連携軸として取り入れやすい。 - ファイターやフィニッシャーなどの過去ベストゴール選手を活かしたスキル構成
過去ランキングイベントで入賞している方は持っている可能性も高く再現しやすい。
ただし補足しておくと、ファイターやフィニッシャーなどの“スタミナ回復系センス”は、カスタムセンスの登場により今後再入手が難しくなる可能性があります。
筆者の構築ではこれらを活かして後半の交代枠を抑える工夫をしていましたが、これから構築する方には再現性がやや下がるかもしれません。
その場合は、前半に発動するチーム連携(タイプスターズ スピードやパワーなど)を優先し、後半は交代枠を活用してテンポを維持する戦術がより現実的です。
スタミナを耐えさせる構成から、試合展開に応じて動かす「交代前提の2段構え構築」へと発想を切り替えると、再現の幅がぐっと広がります。
❗ 再現性が難しい要素
- 鉄壁城塞、阿吽の呼吸などの“強力連携”
対応できる選手が少なく、発動優先度・選手のステータス・連携との両立が難しい。
クラブで固めているユーザー以外は再現性が難しい。 - クラブリンクとチーム連携の両立(前川のような例)
クラブリンク・連携・センスすべて噛み合う選手は限られ、環境によって左右されやすい。
🧠 実践的な代替アプローチ
- ステータス面で劣る選手でも、明確な役割を持たせる
→ 例:筆者の小林や前川など。グレードが低い選手や古いカードでも連携やクラブリンクの力でポテンシャル以上の力を発揮させる。 - 上位プレイヤーが使っている“意外なカード”を調査する
→ 使用率が低いのに上位プレイヤーが使用しているカード、クラブリンクがつかないのに使用しているカードは隠れ強カードの可能性が高い。自分の手持ちにいたら活用法を参考にしてみる。 - “完璧を目指さず、強力な連携の発動を重視する”
→ オフェンス、ディフェンス、チーム連携のフル発動にこだわらず、連携のバランスと発動時間の噛み合わせを優先する方が安定しやすい。
連携に関してはこちら連携 一覧
🎮 アマテラス杯に向けた普段のプレイと準備
アマテラス杯のような真剣勝負の舞台で結果を出すために、筆者が日常的に取り組んでいるプレイ習慣や構築準備のポイントを紹介します。
📅 イベントの達成
- 毎月のイベント報酬は、最終報酬までしっかり回収するのが基本
→ ガチャ券やスパイクなど、構成強化に直結するアイテムを確保 - チャレンジマッチや期間限定イベントも逃さずクリア
→ スタメン候補だけでなく、クラブリンク要員や連携要員のキラ化も優先的に進める
⚽ リアルのJリーグにもアンテナを張る
- 月間MVPやベストゴール選出選手は要注目
→ 低グレードでカードが集めやすい今後伸びてくる若手選手が選手されるケースが多い。 - 今後伸びそうな若手選手は、早めに育成候補としてストック
→ “育成の下地”を前倒ししておくことで、将来的に構成へ無理なく組み込みやすくなる
💪 Jリーグでの実戦経験が構築力を底上げする
- EPを強化して、積極的にJリーグに参戦することを推奨
→ 毎月の猛者との真剣勝負を通じて、構成の穴をが明確に見えてくる - 歴代アマテラス杯優勝者やJリーグ上位常連との対戦
→ 構築力は“猛者との対人実戦の積み重ね”によって磨かれていくと実感している - Jリーグの対戦ログは“構成の健康診断”
→ 毎月の対戦で見つかった弱点を振り返り、次月以降の補強ポイントを明確にしておく
このような日常的な仕込みの積み重ねが、アマテラス杯のような大会で安定した成績を残す土台になります。JリーグのJ1参加は難易度が高いですが、J2であれば難易度が下がります。アマテラス杯で上位、準決勝、決勝に入りたい方はJリーグでの修行が必須と言っても過言ではないです。
💬 これから挑戦するプレイヤーへ
アマテラス杯は、ただの大会イベントではありません。構成を磨き、試合を読み、毎月の積み重ねが試される「構築力の集大成の場」であり、全ユーザーが対象の“真の王者”を決める大会です。
Jリーグのようにエールフラッグによる応援やパワーアップもなければ、逆に相手からのエールフラッグ妨害もない――完全に“自分との戦い”が試される場です。
筆者自身も、過去には思うように勝てず、構成の方向性に迷った時期が何度もありました。
けれども、そうした試行錯誤があったからこそ、「今の自分にしか組めない構成」へとたどり着けたのだと感じています。
最初から完璧な構成や強カードである必要ありません。
まずは「好きなクラブ」や「気に入った選手」から小さく始めて、Jリーグでひとつひとつ答え合わせをしていく。
その過程こそが、やがてアマテラス杯で“自分らしい勝ち方”を生み出す礎になります。
カードプールやアイテムの差は確かにあります。
ですがそれ以上に、発想や工夫、そして最後まで構成を信じ抜けるか――それがこの大会の勝敗を分ける一番のポイントだと思っています。
そして最後には、運も少なからず影響します。
苦手な構築に当たらずスムーズに勝ち進めることもあれば、逆に初戦から苦手構成と当たり続けたり、エースがケガをしてしまうような展開になることもあります。
それでも――そんな理不尽も含めて受け止め勝利したとき、構築は“強さ”から“信頼”に変わります。
あなたのこだわりが、次の大会で誰かの天敵になるかもしれません。
どうか焦らず、自分なりのスタイルで、誇りを持って挑んでください。
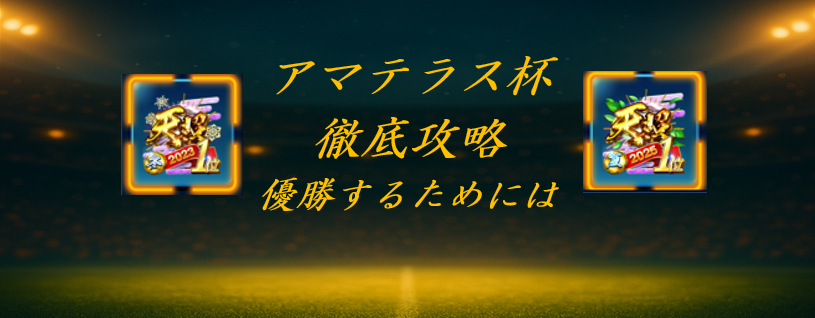
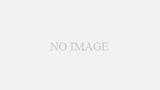

コメント
こんにちは!
いつもイベントでTOP10に入ってらっしゃるので、お名前はお見知りいたしておりました。これほど詳しくJクラについて記されているので、参考にさせていただいてます。
始めて1年半ですが、今週リーグ戦に「チャンス」の印がありました。あきさんの記載で意味を知りました。
自分には無縁と思われていたアマテラス予選に初出場決まりました。まぁ、本戦には進めないでしょうが楽しみです。
今後のご活躍にも期待しています!失礼しました。