🟨序章:連覇達成の報告と、この記事で伝えたいこと
アマテラス杯第8回大会(2025年秋)で、ルーカスあきは連覇を達成しました。前回は「挑戦」、今回は「信念の証明」。ただ勝っただけではありません。構築を信じ抜いたことが勝利に繋がった──その過程を、この記事で共有します。
そしてこの記事は、単なる戦績報告ではありません。「どうすれば勝てる構築が作れるのか?」「カードをどう選ぶべきか?」そんな疑問に、王者の視点から答える内容です。
🧠第1章:構築の再検証──「前回優勝構築では勝てない」Jクラの現実
Jクラは、前回優勝した構築をそのまま使っても勝てない世界です。カードの環境は常に変化し、古いカードは徐々に性能面で不利になっていきます。
今回の大会に向けて、筆者は「構築の強化」を目指しました。そのため、前回優勝メンバーの中でも特に古くなっていた小林祐希(2022年カード)と前川黛也(EPセンス)を一度外し、構築の再検証に踏み切りました。先月のJ1リーグ戦を検証のために使いました。
- 小林 → TSS香川
→ 香川は展開力と個人技に優れ、攻撃は活性化。単体性能としては非常に優秀。 - TSS枠の影響でTSS阿部を外す
→ 守備の要を外したことで、TSSの相手FWを止めることができず失点が増加。 - 前川 → ガーディアン小島
→ 小島はセービング力が高く、単体性能は優秀。しかしクラブリンクが神戸でないため、守備陣を柏軸で構築する必要があった。 - 柏守備陣が揃わず、城塞構築が成立しない
→ ベストゴール犬飼は所持していたが、鉄壁城塞(柏)を組むにはもう一枚足りず、守備が不安定に。 - 結果として守備改善せず
→ 攻撃は強化されたが、守備の崩れが勝敗に直結。 - 構築を戻すという決断
→ 小林・阿部・前川を再起用し、神戸軸の構築に戻すことで守備が再安定。
| ポジション | アマテラス杯夏(前回) | 直前Jリーグ | アマテラス杯秋(今回) |
|---|---|---|---|
| 選手名 | 選手名 | 選手名 | |
| GK | 前川黛也(神戸) | 小島 亨介(柏) | 前川黛也(神戸) |
| CB | トゥーレル(神戸) | トゥーレル(神戸) | トゥーレル(神戸) |
| CB | 犬飼智也(柏) | 犬飼智也(柏) | 阿部勇樹(浦和TSS) |
| SB(左) | 佐々木翔(広島) | 酒井高徳(神戸) | 佐々木翔(広島) |
| SB(右) | 酒井高徳(神戸) | 古賀太陽(柏) | 酒井高徳(神戸) |
| DMF | 大崎玲央(札幌※) | 大崎玲央(札幌※) | 大崎玲央(札幌※) |
| DMF | 阿部勇樹(浦和TSS) | 扇原貴宏(神戸) | 扇原貴宏(神戸) |
| OMF | 小林祐希(神戸) | 香川真司(C大阪TSS) | 小林祐希(神戸) |
| WG(左) | イニエスタ(神戸TSS) | イニエスタ(神戸TSS) | イニエスタ(神戸TSS) |
| WG(右) | 武藤嘉紀(神戸) | 武藤嘉紀(神戸) | 武藤嘉紀(神戸) |
| CF | ダビド ビジャ(神戸TSS) | ダビド ビジャ(神戸TSS) | ダビド ビジャ(神戸TSS) |
| オフェンス連携 | |||
| ディフェンス連携 | 城塞構築 神戸 | 城塞構築 柏 | 城塞構築 神戸 |
| チーム連携 | タイプスターズテクニック | クラブスターズ 神戸 | タイプスターズテクニック |
この検証から得た教訓は、「構築とは個の強さではなく、全体の調和」ということ。TSS香川もガーディアン小島も、単体では非常に強力なカードでした。しかし、筆者の神戸軸のチームでは、もともと攻撃力はあったことと小林と前川の方がクラブリンクとチーム連携の面で優れており、全体のバランスが良かった。
読者の皆さんも、カードの性能だけでなく、構築全体のバランスを意識することで、勝率が大きく変わります。
🧩第2章:キーマンの再評価──小林祐希と前川黛也がなぜ戻ったのか
構築検証の結果、筆者は小林祐希と前川黛也を再びスタメンに戻しました。この判断は、単なる“戻し”ではなく、構築の本質を見極めた上での再評価です。
小林祐希(2022年カード)は、確かに古い。しかし、神戸軸の構築においては、スペクタクルFKが攻撃の起点として機能し、決勝でも2アシストを記録しました。古いカードでも、構築に合えば十分に活躍できる──それを証明する存在です。
前川黛也も同様。EPセンスで物足りなさを感じる場面はありましたが、神戸守備陣とのクラブリンクが安定感を生みました。小島のような高性能GKを活かすには柏軸が必要ですが、それが成立しないなら、構築全体の安定を優先すべきと感じました。
ここで伝えたいのは、「強いカード」より「噛み合うカード」を選ぶことの重要性。読者の皆さんも、構築の軸に合わせてカードを選ぶことで、安定した戦いが可能になります。
⚙️第3章:神戸純正軸構築の基本設計──4-3-3B+カウンターの強み
筆者が採用したのは「4-3-3B」+「カウンター戦術」。この組み合わせは、前回の記事でもおすすめしましたが、守備の安定と攻撃の鋭さを両立できる構成です。
さらに、神戸純正軸構築にこだわった理由は以下の通り:
- クラブリンクによる連携発動率が高い
- 単純にクラブリンクでステータスが上がる
- 手持ちカードの大半が神戸でありセンスも揃っている
- ビジャを軸にした攻撃設計が完成されている
初心者や中級者でも真似しやすい、意識してほしいのは「まずはクラブを揃える」ことが構築の第一歩になります。
J1チームは選手層も豊富になってきており、J1のクラブであればかなり強い構築を組めるようになります。直近も湘南(上福元:96、鈴木:99、ミンテ:95、畑:93)や岡山の守備陣(96ブローダーセン:96、立田:95)など魅力的なカードが多くなりました。
もしくは、TSSなどのエースを軸にクラブやチームセンスを揃えた構築にすることで勝率を上げることができます。
筆者の場合は、CFのTSSビジャを軸にビジャにボールが集まる構成、神戸守備陣を中心に連携を発生させる構成で攻守のバランスを取っています。
🧮第4章:TSS枠とクラブリンク──構築設計の実践ノウハウ
TSS枠は強力なカードを使える反面、構築の自由度を制限します。筆者の香川を入れることで阿部を外す必要が生じ、守備が崩れたのはその典型例です。
TSSをどこで使うのか3枠を有効に使うことでチームバランスを保ち、勝率を上げることに繋がります。
筆者は攻撃に偏りすぎたことでバランスが崩れました。
読者への実践的アドバイス:
- TSS枠は「誰を入れるか」だけでなく「誰を外すことになるか」まで考える
- チームの弱点にTSS枠を使用する
- 構築は「強いカードを詰め込む」より「噛み合うカードで揃える」方が安定する
🧠第5章:構築を信じるとは何か──決勝戦の判断
決勝戦では試合前からPK戦に入れば負ける可能性があると感じていました。PKには自信がありましたが、唯一PK負けの可能性がある相手だったので、構築を崩してPK勝ちに行く構成に変更する選択肢もありました。
ですが、あえて変更しませんでした。「構築の強さを証明するため」に戦う──腹をくくりました。
あなたなら、構築を変えますか?それとも、信じて貫きますか?
筆者は結果的に変更しなかった(信じて貫いた)ことで、試合時間内の逆転優勝に繋がったと感じています。
🔚終章:進化と信念の証明──連覇の意味と次への布石
今回の連覇は、前回の優勝構築をそのまま使った結果ではありません。環境の変化に合わせて構築を見直し、試して、崩れて、戻して──その繰り返しの中で、少しずつ形になっていったものです。
強いカードを並べるだけでは勝てません。構築は、選手の性能だけでなく、選手同士の相性を形にするものだと思っています。
そして最後に必要だったのは、「信じて貫くこと」。試合前に不安があっても、構築を崩さずに戦ったことで、結果的に逆転優勝に繋がりました。
この経験が、読者の皆さんの構築づくりにも何かヒントになれば嬉しいです。
今回は前回優勝からの試行錯誤、バランスの重要性、信じて貫くことについて書きました。
次回はどうやって構築を考えるか、どう実戦で検証するかを詳しく解説できればと思います。
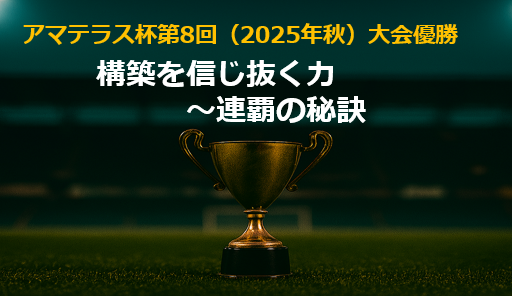
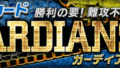
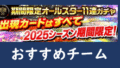
コメント